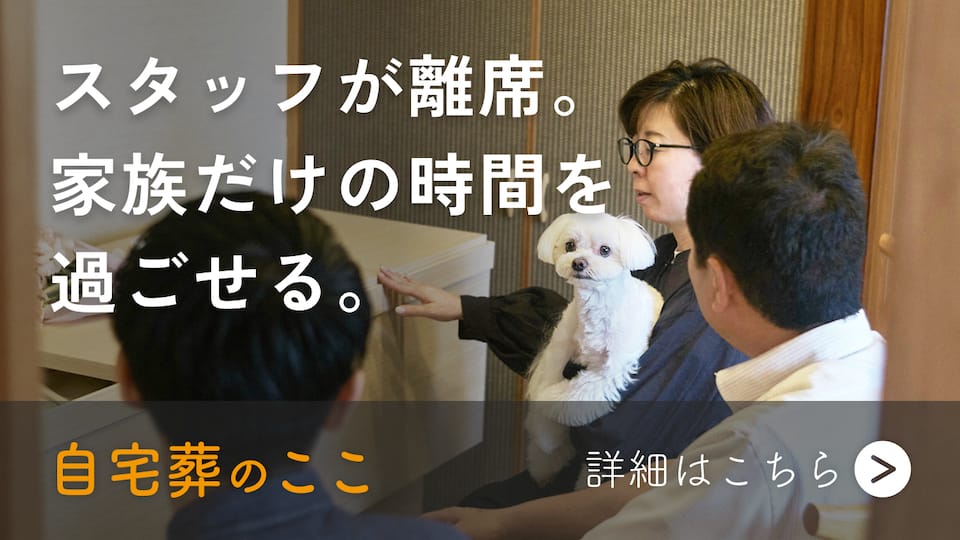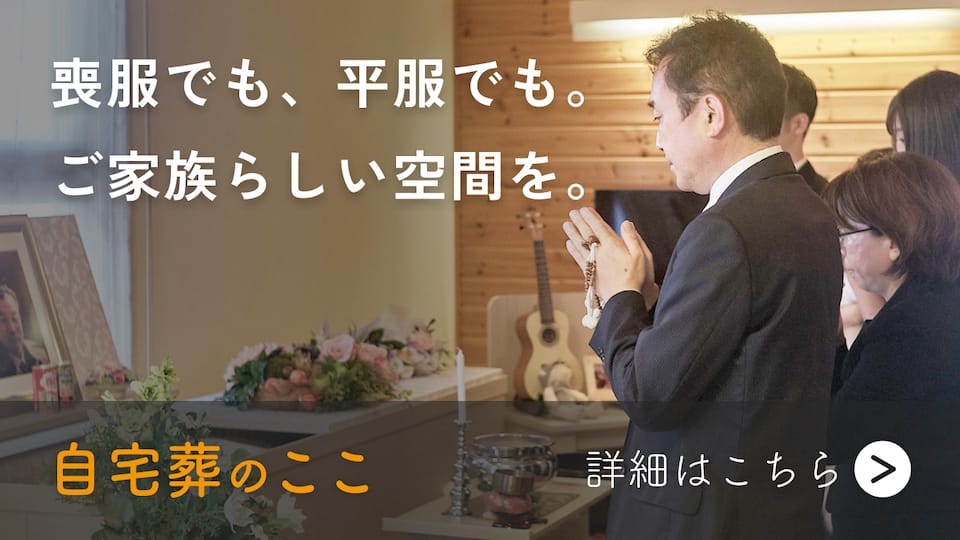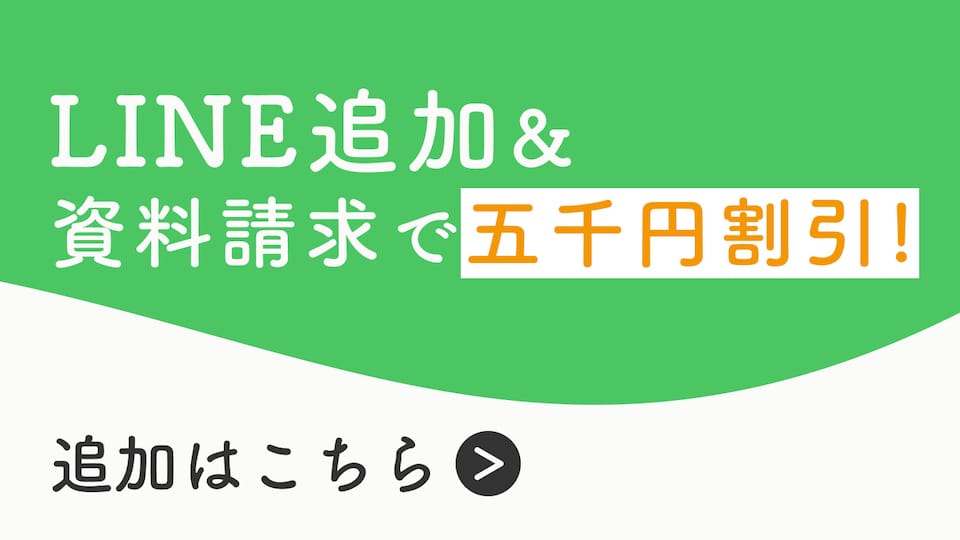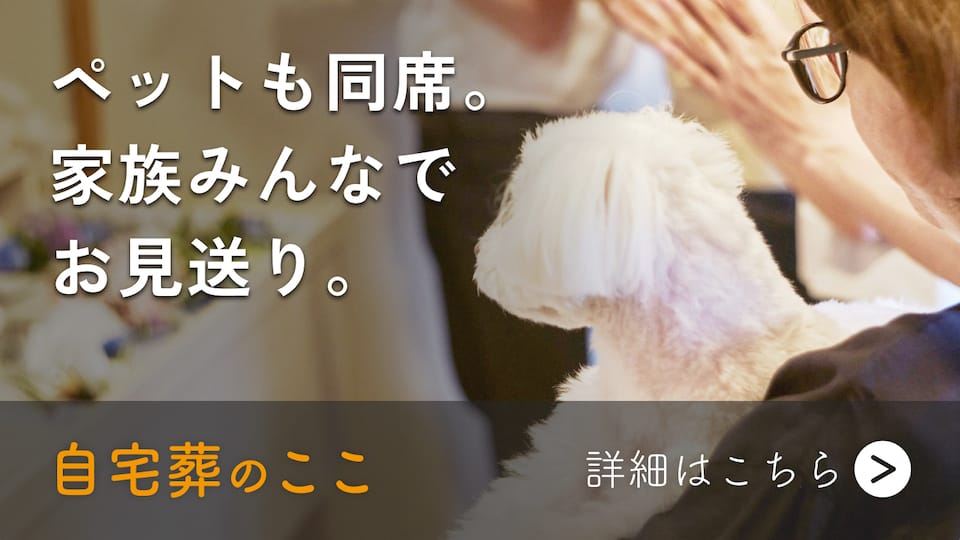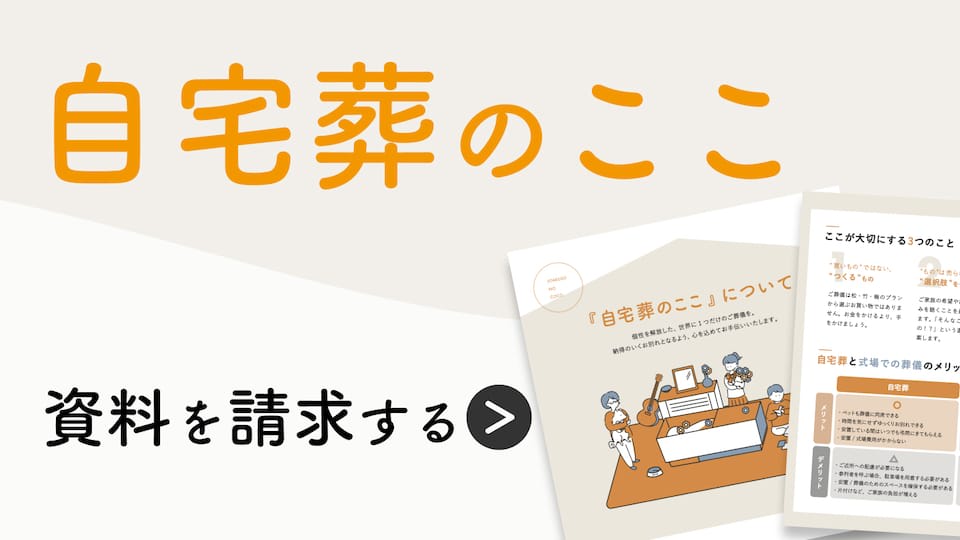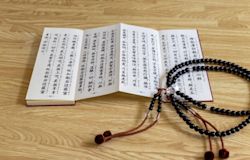家族が亡くなってから自宅で葬儀するまでの流れや必要な日数は?

自宅葬はもともと一般的な葬儀の形でしたが、近年は葬儀会館が主流になっています。そのため、自宅葬の流れがよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では自宅葬を行うために必要な基本的な流れや、自宅葬で慌てないための準備について詳しく解説しています。自宅の整理やマンションの場合の注意点、葬儀費用の準備なども詳しく説明していますので、自宅葬について詳しく知りたい方や、将来自宅葬を行う可能性がある方はぜひ最後までお読みください。
亡くなってから自宅での葬儀までの基本的な流れ
亡くなった方を自宅でお見送りすることは、日本の伝統的な方法のひとつです。お亡くなりになる方のほとんどは病院のため、ここでは病院で近親者が亡くなった場合から自宅で葬儀するまでの基本的な流れについて説明しています。
葬儀会社に連絡
病院で医師から死亡を伝えられると、できるだけ早めに病院をでなければなりません。そのため 死亡を確認したあと、すぐに遺体の搬送を葬儀会社へ手配する必要があります 。
葬儀会社が決まっていない場合、病院で紹介してもらえます。とりあえず遺体の搬送だけをお願いし、葬儀は別の葬儀会社に頼むことも可能です。
遺体の搬送・自宅に安置
葬儀社が専用の車両で遺体を搬送し、自宅に安置します。遺体は遺族の希望により寝室や和室に棺桶を置いて安置されます。
このとき主な遺族は病院にいて、自宅を整理することができません。 親族などに依頼して自宅を整理してもらい、棺を運ぶ通路や置く場所を確保しておく とスムーズです。
死亡届・火葬許可申請書の提出
死亡届と火葬許可書は市・区役所へ死亡を知った日から 7日以内 に提出します。死亡届は病院からもらう死亡診断書についてくるため、必要事項を記載して市・区役所へ提出します。すると火葬許可証をもらえます。火葬許可証がないと、火葬ができません。
遺族が亡くなり忙しい家族のために、多くの場合は葬儀社が代行で申請してくれます。
訃報の連絡
通夜や葬儀の日時が決まったら、 親族や知人に電話やメール、メッセージなどで訃報をお知らせします 。家族や近い親戚、菩提寺などには電話で伝えた方がいいでしょう。
故人の会社へ連絡する際は、直属の上司に伝えるのが一般的です。

参列者の駐車場等の確保
参列者のために、駐車場などの手配をします。自宅葬の場合、近隣住民に迷惑をかけないよう、駐車場を確保する必要があります。
近所のコインパーキングなど、訃報の連絡をする際に伝えておくとトラブルを防げます 。
ご近所に葬儀を自宅で行う旨の挨拶
葬儀を自宅で行う場合は、 ご近所への挨拶 も忘れないようにしましょう。葬儀の旨を報告し、葬儀に伴う騒音や駐車場の利用などで、ご迷惑をかける場合があるかもしれないことをあらかじめ断っておくことで、ご近所とのトラブルを最小限に抑えられます。
通夜・告別式
自宅葬でも通夜や告別式の流れは、葬儀会館と代わりはありません。 亡くなって1~3日目にはお通夜が行われ、お通夜の翌日に告別式が行われる場合がほとんど です。
自宅葬の場合、会館のように時間などの制約はありません。故人とゆっくりお別れができる大きなメリットがあります。
火葬
告別式が終わると、棺を霊柩車や寝台車に乗せて火葬場へ向かいます。 火葬場へは遺族や親族が付き添い、自宅の祭壇などは葬儀社が片付けてくれます 。
火葬が終わった遺骨は、納骨まで後飾り祭壇に安置されます。
亡くなってから葬儀にかかる時間・日数
法律では、亡くなってから24時間以内の火葬が禁止 されています。そのため葬儀の時間を決めるのには工夫が必要です。。
亡くなった翌日に通夜が行われ、翌々日に葬儀が行われるのが一般的ですが、友引を避けたり、親族の予定が合わなかったりする場合、通夜や葬儀の日程を延ばすこともあります。とくに最近では、火葬場の予約が思うように取れず日程が延びるケースが多く見られます。
遺族が遠くに住んでいる場合など、最後の挨拶をするために1週間以上葬儀を先にすることもめずらしくありません。
亡くなってから葬儀で慌てないための準備
家族が危篤状態にある場合や高齢の家族がいる場合は、亡くなってから慌てないために、 自宅をいつも片付けておく など、準備をすすめておくことも必要です。
自宅葬を考えているなら、あらかじめ準備しておくとよいことを4つご紹介します。
自宅の整理
自宅葬をしない場合でも、最後は家に連れて帰ってあげたいと通夜を自宅で行う場合もあります。
ご遺体を自宅にお連れする場合、ご遺体を寝かせる場所や棺を置く場所を確保しなければなりません。ご遺体が家に帰ると、通夜では家族や親族、知人や近所の方が集まります。
ご遺体を置く場所だけでなく、お悔やみに来てくれた方をおもてなしする場所も必要になります。 できるだけ物を減らして、人が入れるスペースを作っておきましょう 。
自宅葬を行う場合は、祭壇を飾る場所や受付の場所、食事をする場合は食事の場所などが必要になります。あらかじめスペースは十分にあるかを検討するのが大切です。
マンションの場合は管理会社に確認
マンション住まいの場合、故人や家族が自宅葬を望んでも、マンションの規約で自宅葬ができない場合があります。
事前に自宅で葬儀をしても大丈夫か、棺の搬入経路(エレベーターにトランクがついているか否か)など管理会社に確認しておきましょう 。
エレベーターで棺を運べない場合、階段で運ばないといけなくなります。重い棺を運ぶのは大変で、ご遺体も傾きやすいためおすすめはできません。
また管理会社が問題なくても、人の出入りが多くなるなど近隣への迷惑は避けられません。とくにマンションの場合隣の出入り口や窓が近く、騒音や焼香の煙などの問題があります。管理会社に確認するとともに、近隣の部屋と普段から良好な関係を保つよう心がけましょう。

葬儀費用の準備
葬儀費用は一般的に葬儀が終了してから支払います。 逝去から葬儀までは3日〜5日ほどの場合が多いので、それまでにお金を準備しておく必要があります 。
自宅葬の費用は、葬儀会社に依頼する場合と自分で行う場合で異なります。葬儀会社に依頼する場合は、会社やパッケージによって異なりますが、一般的には40万円ほどからとなっています。
一方、自分で行う場合は、宗教儀礼なしで火葬だけだと10万円ほどで行えます。ただし遺体の搬送・管理・供養に必要なものや、来客者のための飲食物や椅子などの手配まで自分たちで行う必要があるため、すべてをお任せできる葬儀社を利用する方がほとんどです。
葬儀場を借りるお葬式の場合、100万円以上かかるといわれているため、会場費用がかからない自宅葬は葬儀社を利用したとしても、葬儀費用の節約になります。
葬儀社の決定
病院で亡くなった場合、すぐに遺体を移動する必要があります 。その際、遺体搬送を請け負っているのが葬儀社です。搬送だけのお願いも可能ですが、あらかじめ葬儀社が決まっていると、すべての手続きを一社に頼めるので手間が省けます。
大切な方が亡くなった場合、遺族はそれだけで精神的に負担を感じています。葬儀の手配は、遺族自身ですべて準備することは難しく、葬儀社に依頼することでスムーズな葬儀を行えます。信頼してすべておまかせできる葬儀社を見つけておくと、いざというとき心強いサポートとなります。
なお、葬儀社によっては自宅葬を受け付けていないところもあります。ここに依頼したいと目星をつけた葬儀社があれば事前に問い合わせ、自宅葬を受け付けているかどうかだけでも聞いておきましょう。
まとめ
近親者が亡くなってから自宅で葬儀をするまでの基本的な流れを説明しました。
葬儀はあらかじめ予定を立てられるものではありません。しかしいざという時のためにある程度の準備をしておくことで、遺族の負担は軽減され故人に敬意を示す心からの葬儀を行えます。
自宅で葬儀を執り行う際は、スペースの確保や近隣住民への配慮などに気を配りできるだけトラブルなく大切な方をお送りしたいですね。