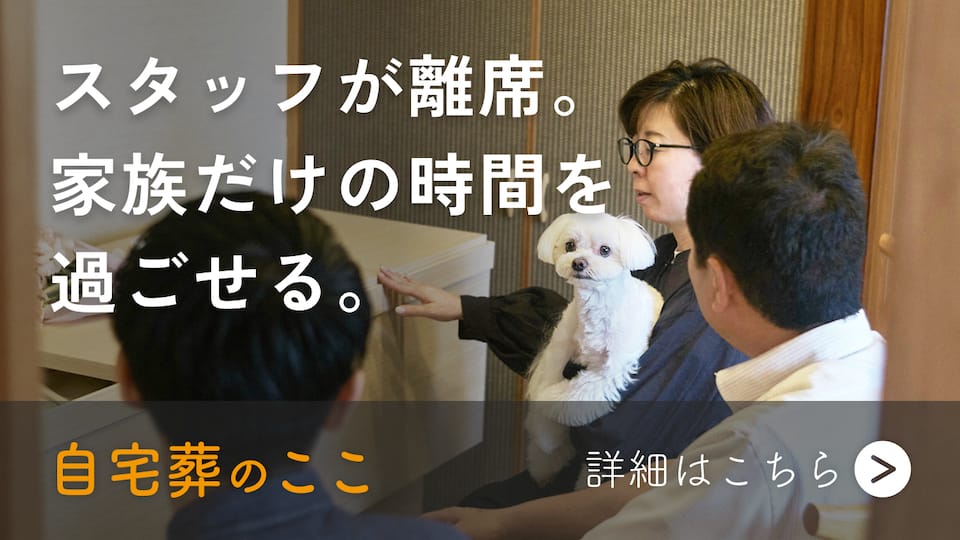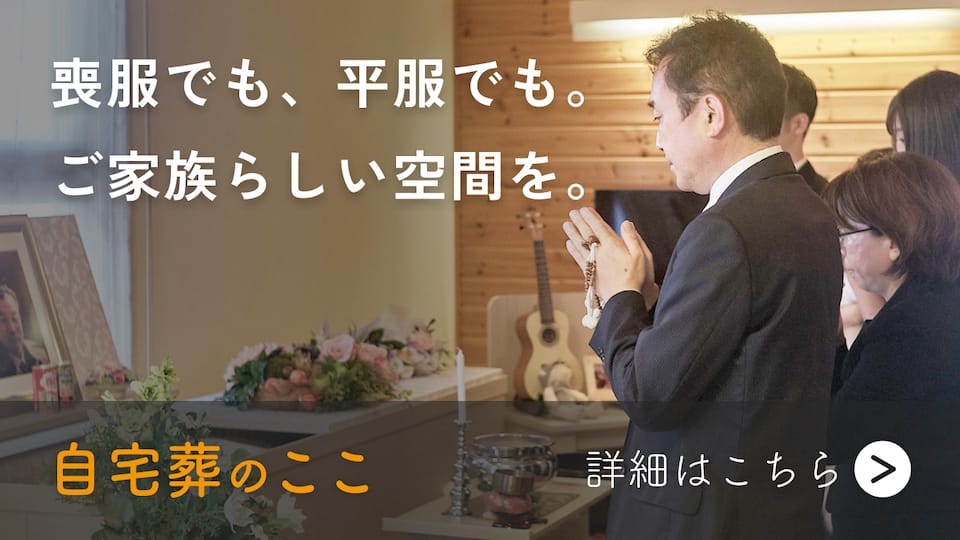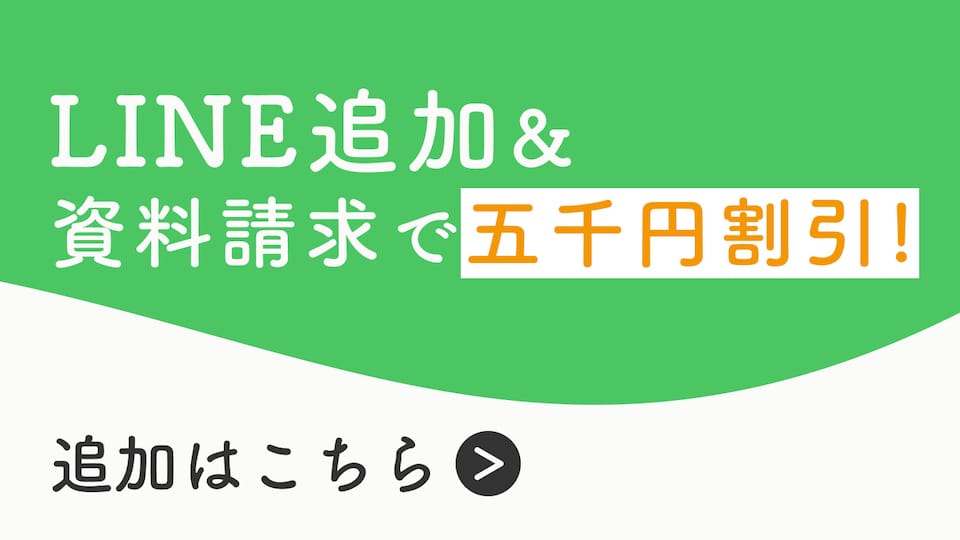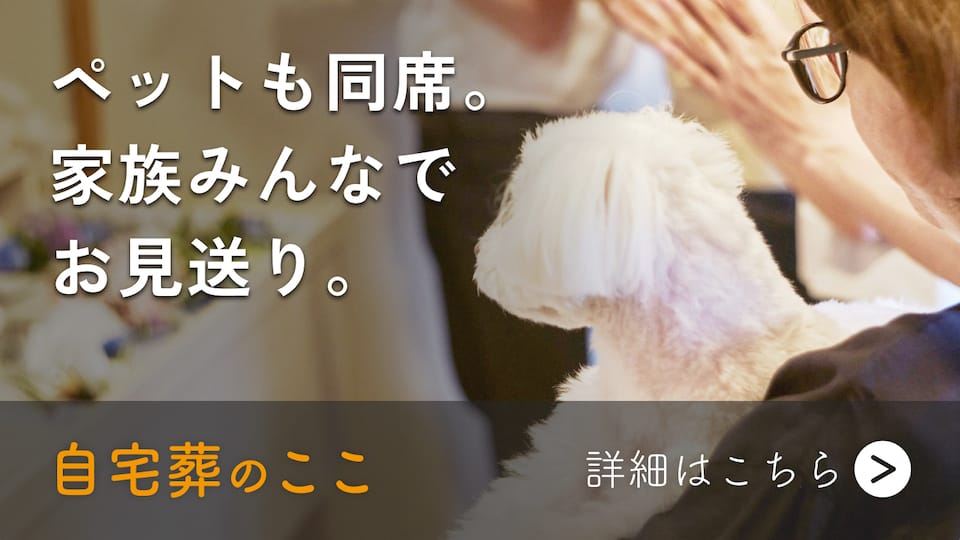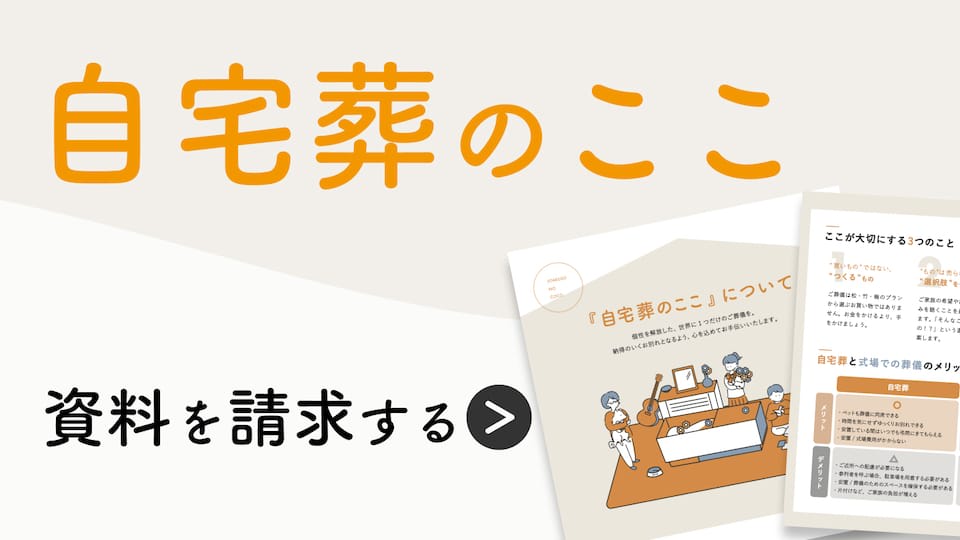「枕経」とは?意味を理解して必要なものや流れを知ろう
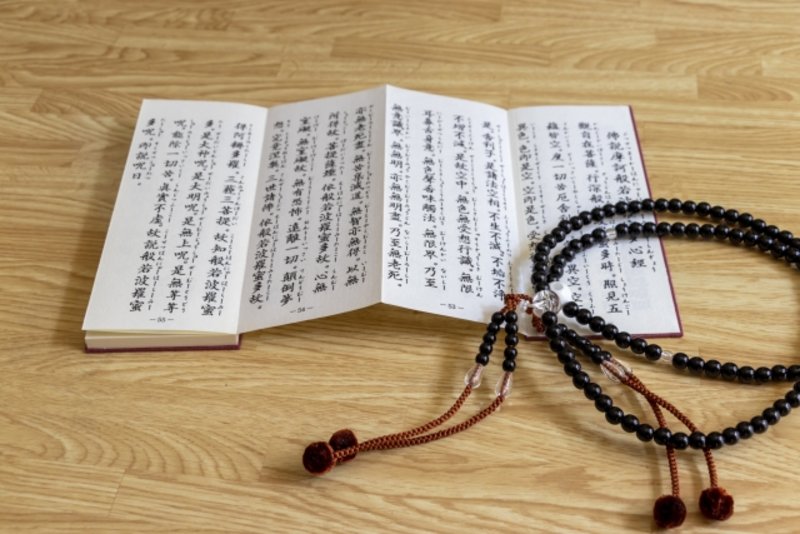
「枕経(まくらぎょう・まくらきょう)」という言葉は、あまり知られておらず、どのように執り行なえばいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。
枕経とは、故人の枕元でお経を読むこと です。
この記事では、枕経についての意味や由来から、枕経に必要なもの、流れまで簡単に解説しています。
またマナーについても説明していますので、枕経に参列するかもしれない方は、ぜひ最後までお読みください。
枕経について
枕経とは
枕経とは、 納棺までの間に故人の枕元で読経すること です。
仏教の教義に基づく善行の一環であり、敬意と深い思いやりを込めて行われる大切な儀式でもあります。
枕経をあげるタイミング
現代では、亡くなった直後から納棺までの間に行われることが多くなっています 。
かつては、安らかに旅立てることを願い、自宅での臨終の際に読むのが一般的でした。しかし、現代では病院で最期を迎えることが多く、このタイミングで行われるようになっています。
しかし、具体的なタイミングについて厳格な決まりはなく、地域や慣習によっても異なります。迷った場合は、僧侶や葬儀社と相談してみるとよいでしょう。
枕経の目的
臨終間近に居合わせた人の心の平穏、あるいは臨終後の故人の浄土への旅の道しるべとすることが目的とされています。
枕経の由来
枕経は、平安時代に浄土教の僧侶がはじめたとされています。
ほかにも諸説伝えられていますが、江戸幕府の儀礼を解説している『徳川盛世禄』には、中流社会の葬儀で枕経について書かれている箇所があるため、少なくとも江戸時代には行われていたことがわかります。
キリスト教が禁止されていた江戸時代には、遺体の検査としての意味もあったようです。
枕経のお経の種類
枕経は、仏教の経典のひとつであり、 宗派によって読まれるお経は異なります 。
- 真言宗
「般若波羅蜜多心経(はんにゃはらみったしんぎょう)」「阿弥陀経(あみだきょう)」「陀羅尼(だらに」などのお経が読まれます。唱えるのは「南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)」です。
- 曹洞宗
地域によって異りますが、「仏垂般涅槃略説教誡経(ぶっしはつねはんりゃくせっきょうかいきょう)」「参同契(さんどうかい)」「宝鏡三昧(ほうきょうざんまい)」などが読まれることが多いようです。
- 日蓮宗
法華経の「方便品(ほうべんぽん)」などがよく読まれます。また「南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」が唱えられます。

枕経で必要なもの
葬儀社が準備してくれるものもあるため、基本的には 葬儀社から「〇〇をご用意ください」といわれたものを用意すればいいでしょう 。
ここでは、代表的に枕経に必要なものを紹介します。
香炉、燭台、花立、花
これらは 枕飾りに必要なもの です。
枕飾りとは、枕元に設置する祭壇のこと です。
お香を焚く「香炉(こうろ)」、蝋燭を立てる「燭台(しょくだい)」、花を生ける「花立(はなたて)」の三つは 「三具足(みつぐそく・さんぐそく)」 と呼ばれます。
小型の机などに白布をかけ、香炉や燭台を置きます。そして机の脇には、一対の花束を飾ります。
そのほか、宗派によっては掛け軸などが飾られます。
枕飾りに必要なものは葬儀社で用意してくれる場合も多いため、 準備する前に葬儀社に相談してみるといいでしょう 。
僧侶の座布団とお茶菓子
枕経をあげる僧侶が座る、座布団を用意しておきます 。
座布団は、一般の座布団より大きく厚みのある、仏壇用座布団を用意するのが好ましいでしょう。
また枕経が終わった後、僧侶へ出すお茶とお茶菓子も用意する必要があります。
お茶は必ず茶托(ちゃたく)を使い、お菓子は菓子皿に懐紙(かいし)を乗せてお出しするのが理想ですが、忙しく準備が間に合わない場合は、その限りではありません。
僧侶へのお車代
枕経の場合、僧侶へはお布施ではなく 「お車代」を渡します 。お車代は、いわば交通費です。
お車代の相場は、5,000円から1万円ほどとされています。封筒の表書きは「御車代」としてください。
お車代は枕経が終わってから渡します。

枕経の流れ
ここでは、枕経をあげるまでの流れをご紹介します。
- 遺体の安置場所の確保
- 菩提寺の僧侶に連絡
- 枕飾りの設置
- 僧侶の到着後の挨拶
- 僧侶の枕経
- 僧侶への今後の儀式の相談
順番に解説します。
遺体の安置場所の確保
遺体の安置場所の確保は、枕経の準備として大切です。
一般的に安置場所は、葬儀社保有の安置施設や自宅が選ばれます 。
安置施設には、遺体を安置するための特別なスペースが用意されています。一方自宅の場合は、遺体を安置する場所を確保する必要があります。
遺体の安置場所は、家族や知人が静かに最期を送れて、枕経を行うための余分なスペースがある場所を選んでください。
菩提寺の僧侶に連絡
枕経をあげるために、 菩提寺の僧侶を呼ぶ必要があります 。
菩提寺がない場合、または菩提寺の都合がつかない場合は、葬儀社に確認しましょう。
菩提寺に連絡する際には、故人の名前、死亡時間、享年などを伝えます。
また、枕経をあげてほしいという目的を明確に伝えることが大切です。
伝える際の文章例
いつもお世話になっております。〇〇の家族の者です。
〇〇が〇月〇日〇時に亡くなりました。享年〇〇でした。
ただ今、〇〇(葬儀場名または自宅)へ戻りましたので、枕経をお願いしたいと思います。
枕飾りの設置
小型の机などに白布をかけ、線香を焚くための香炉や燭台、線香立てを置きます。そして経机の脇に一対の花束を飾ります。
枕飾りの設置によって、僧侶を迎える準備を行いましょう。
僧侶の到着後の挨拶
僧侶が到着したら、まず挨拶をします。
また「何分不慣れでございますので、ご指導よろしくお願いいたします。」と付け加えておくと、不備があった場合教えてもらえるでしょう。
お忙しい中、ご足労いただきまして誠にありがとうございます。
何分不慣れでございますので、ご指導よろしくお願いいたします。
僧侶の枕経
僧侶への挨拶が終わった後、僧侶の枕経が行われます。所要時間は30〜40分程度が相場です。
僧侶への今後の儀式の相談
枕経の後は、僧侶にお茶やお菓子を出して、通夜や葬儀の日程、戒名などの相談を行います。
また、このタイミングでお車代をお渡しするようにしましょう。なお、お車代は小さなお盆の上に乗せて渡すのがマナーです。
枕経に参列するマナー
枕経は近親者のみで行われることがほとんどのため、 厳格なマナーはありません 。
故人が安らかに眠れるよう、心静かに枕経を聞くことが大切です。
服装:地味な平服でOK
枕経の服装は、 喪服ではなく地味な平服 です。
枕経は、亡くなってできるだけ早めに行う儀式なので、参加者はほとんど近親者のみとなります。
そのため、派手な色や派手な模様の服を避ければ、日常着ている服で構いません。
数珠はできるだけ用意
数珠は故人への敬意を表すものとされており、お通夜やご葬儀でも必要になりますので、バッグの中に常に入れておくと良いでしょう。
ただし忘れてしまった場合でも、枕経に参列できないというわけではありません。

香典は不要
枕経に参列する場合、 香典は必要ありません 。
香典には、儀式の金銭的なサポートという目的があります。そのため、近親者のみで行われる枕経においては、香典の持参は必要ないとされています。
香典は、枕経の後に行われるお通夜や葬儀の際にお渡しすればいいでしょう。
まとめ
枕経はあまり知られていませんが、故人が亡くなって最初に読まれるお経となるため、重要な仏教儀式です。
しかしお通夜やお葬式より参列する機会も少なく、あまり知られていません。
大切な人を亡くし、動揺しているときに行われる儀式であり、「何をしたらいいかわからない」とならないために、本記事が枕経を知る機会となれば幸いです。
新しい「故人を偲ぶ」形
本記事をご覧になった方の中には、故人との別れに際し、遣る瀬なさや寂しさを抱いている方もいらっしゃるかと思います。
この想いの行き先として、距離と時間を越えて故人の思い出を共有し合い、故人を悼む時間をお過ごしいただける 3日限りの追悼サイト作成サービス 葬想式 をご紹介します。
葬想式は招待制の追悼サイトを無料で簡単に作れるサービスです。
招待された人々がサイトに集い、思い出の写真やメッセージを投稿できます。公開期間中(3日間)はいつでも、どこからでもサイトにアクセス可能で他の参加者の写真やメッセージも見ることができます。参加人数、投稿写真枚数、メッセージの数は無制限、無料でご利用いただけます。
今は亡き大切な人に想いを馳せながら、どの写真を投稿しようか昔のカメラロールを遡ったり、伝えたい言葉を紡いだりすることで、大切な人がもう亡くなった日常へと進む第一歩になるかもしれません。
昔のお写真がお手元になくても、言葉を綴ることはできます。たくさんの思い出で溢れる素敵な場で偲ぶ時間を過ごされてはいかがでしょうか?
招待文を作るのが難しいなど、葬想式を開式する上でのハードルを乗り越えるお手伝いをさせていただきます。
こちらの公式LINEからお気軽にお問い合わせください。
また、こちらの葬想式公式サイトより、パンフレットの送付請求やサンプルページの閲覧が可能です。こちらも是非ご活用ください。
本記事が大切な人とのお別れを諦めない一助になりましたら冥利に尽きます。