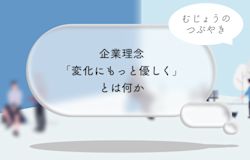連載:トイナオ死 #1「無常観を問い直す」話:株式会社むじょう 前田陽汰

大きな消費的な時代の流れの中に我々は飲み込まれ、問うべき重要なことと向き合えていないのではないか——— そうした危機感から、人々が死をはじめとした根源的な問い(自らの人生の理想的なあり方や幸福観、死生観など)に向き合う機会を作ること、つまり人々が「生きること、死ぬということを問い直す」ための一助となること、「死を問い直す」ことをテーマに掲げ、本連載『トイナオ死』は始まった。
第二回である今回は、株式会社むじょうの代表である前田陽汰をたずねた。前田は、「葬想式」や「死んだ父の日展」などの事業を通じて、「無常観というメンタリティを日常に溶かす」ことを目指し活動している。
死を問い直すことの第一線にいる前田にとって現代社会において「死」というものがどのようにうつっているのかを語ってもらった。
ネガティブな変化に優しいまなざしを向けること
——— まずは前田さんが代表をなさっている株式会社むじょうでの活動について伺っていこうと思います。HPを拝見したところ、むじょうではvisionとして「変化にもっとやさしく」が、そして「右肩上がりを問い直す」「他者の合理性に思いを馳せる」「インターネットに血を通わす」がpolicyとして掲げられています。これらの言葉の意味について伺いたいです。
社名が「むじょう」(無常)です。つまり「常はない」という前提に立ち、常に同じものは無いという世界の捉え方をすると、 世界は常に変化し続けている ことになります。
いろんな変化がありますよね。人間が生まれてから成長していくのも変化だし、成長を積み重ねていくといつしか老いていくのも変化だし。とにかく人は変わり続ける。
その中でも、まなざしが向けられない変化、向けづらい変化ってありますよね。例えば、弱っていく人っていうのは、喜んで直視したいものではないですよね。

——— そうですね。見ていて辛くなることもあります。
「エモい」という感覚にならないものかもしれません。何かがなくなってしまうことや、なくなっていくのが悲しいことなどですね。昔遊んでいた公園がなくなっちゃったり、柵などで囲われて工事中だったりしますよね。そういうのを目にして、「思い出がまた一つなくなってしまう」と思うような、そういうような変化ってあまり見たくない。
でも、そういう変化も、みんなが喜んで直視している変化と同じ「変化」なんだと思います。最初に言ったように、世界の全ては変化している。嬉しい変化も悲しい変化も、同じ変化であると。
だから、片方を照らして、もう片方を隠す…みたいな見方をするのではなく、 見たくない変化にも優しい眼差しを向けてあげる余地があるんじゃないか という投げかけですね。逆に、そういうまなざしを向けないと、人口が減って縮退していくこれから、しんどくなるんじゃないかと思います。そういう意味で「変化にもっと優しく」ですね。
——— なるほど。ここまで伺っていて、「変化にもっと優しく」という言葉の背景には現代が「優しくない」という意識があるのでは、と思ったのですが、もし「優しくない」のだとすれば、それはどういうところだと思いますか?
例えばですが、使われる言葉が優しくないですよね。「限界集落」とか「消滅可能性都市」とか。「消滅」や「限界」は社会通念上ネガティブとされる側にあるじゃないですか。そういうものに冷たさを感じる。「廃盤」とかもそうですね。
一方で、優しい言葉もある。「アンティーク」とかは、希少価値があるということが付与される。全ての言葉が冷たいわけじゃない。でも、「アンティーク」は海外からの言葉で、日本の言葉じゃないんですよね。海外では苔むしたものに価値をおいた言葉がいくつかあるけど、日本だと「味がある」という言葉があるものの、総じてネガティブな言葉ですよね。それが悪いと言いたいのではなく、風潮として、日本にはそういう文化がある。
「撤退」とか「解散」とかも、あまりきれいな言葉じゃないですね。「撤」に「退く」、「解散」も「解く」に「散る」だし。
——— 変化の中でも、特に目を背けたくなるような変化にはあまりポジティブな言葉が使われている印象はないですね。そういう変化も受け入れていくべきだと。
「受け入れる」というよりは、ある種の選択肢の提示、投げかけですね。別の目線を向けることもできるんじゃないかという提案ですね。 僕らにできるのはそれくらい だと思います。
———では、そのようなvisionは「右肩上がり」とどう関わってくるのでしょうか?
「右肩上がり」はわかりやすいと思います。「成長すればいいよね」という足し算的な発想。資本主義というのはそれがないと成り立たないわけだけれど、その右肩上がりの直線から漏れていく、右肩下がっていく線もたくさんある。上がっていくことばかりが「良いよね」と言われていると、下がっていく人も上を目指さなければならなくなる。もはやそういう風潮がありますよね。
「足るを知る」というようなメンタリティは美しいけれど、あまり迎合されていない気がします。小学校や中学校でも「この点数が取れたら次はこれを目指そう」となるし、「これでいいんだ」とはなりませんよね。限度があった方が幸せという考え方はあまりありません。
———では、続いてそうした考えを社会に広めていくためにどう実装、実行していくかについて伺っていきたいと思います。むじょうでは、インターネットを用いたプロジェクトが多いように思いますが。
インターネットの向こう側にいる人たちって、不特定多数の人たちに発信できる分、手紙みたいな手触り感がないですよね。例えば、この記事みたいなオウンドメディアも、記事を書いてネット上に記事をアップロードするわけだけど。その時一般的にはGoogleのアルゴリズムで上位表示されるためにSEO対策をやるわけだけど、そういうアルゴリズムを過度に気にしすぎると、人間に向けて書くというよりGoogleに向けて書いていることになる。でも、それって意味があるんだろうか。
むじょうの思想としては、一番上に上がらなくてもいいから、血の通ったものを二番目、三番目においておこうよ、というものです。そっちの方が、血が通っていて欲しいところに通っているというか、切実度が違うと思います。量産型でアルゴリズムのために書いた記事と、「こういう人のために書きたい」と読む人の顔を想像しながら書く記事は全然違う印象を与えるはずだし、そういうのは読者もわかる。これは血が通っているな、とかそうでないとか。 血を通わせたものを届ける 。そういうことを信条にしているからこそ、policyにそう(「インターネットの血を通わす」)書いている。
インターネットに限らず、これはいろんなこと、例えばご高齢の方でも使い易いUXを考えることや、電車の中で席を譲ることと同じだと思う。向こう側のこと、相手側のことを考える。現実世界と同じように、相手の立場からインターネットのサービスを作りたいと思っています。

現代は生きることの希少価値が下がっている
——— ここまでむじょうとしての前田さんの活動を伺ってきましたが、今度は前田さん個人としての問題意識を伺っていきたいと思います。大学では最近、死や死生観の研究に取り組まれていると伺っていました。命は誰のものかといった問いに代表されるような、死生観が持つ現代での役割、人々からの受け止められ方とこれからについて伺っても良いでしょうか。
今か。難しいですね。まずは少し前のことを考えてみましょう。医療は少しでも死なないように、生きやすいように進化してきました。それで達成されたのが、死ななくていい社会ですよね。少しの病気なら治せるし、ずっと生きやすくなった。
生きることを渇望していた時代 から、今度は切実に生きたいと思いづらい、 死ぬことを想像しづらい時代 になった。死ぬことを想像できない。生きることは尊いということは道徳の授業では習うけど、リアリティがない。
現代はさっきも言ったように、死というのは相変わらずよくわからない、わからないから怖いということもあるだろうけど、現実感がない。「野垂れ死ぬ」という言葉があるけど、人が野垂れ死ぬことはなくなった。
でも「野垂れ死ぬ」という言葉があるということはかつて野垂れ死んでいた人がたくさんいたわけで。今もその言葉が残っているということは、人々が野垂れ死んでいたのは大して昔でないということですよね。死を排除することに成功したのが、今なのかなと思います。
それで、これからどうなっていくかという話ですが、死はまずます身近なものがなくなっていくと思います。死に場所も家から病院へ移り、特定の場所になってしまった。
これからますます生きられる時間は延びていくと思うけれど、「何のために生きているか」という問いはより重要な問いになってくると思います。より生きられるようになったけど、そもそもなんで生きているんだっけ、という感覚に陥りやすいのではないでしょうか。生きることの希少価値が、下がっている。
これからどうなるかはわかりませんが、どうなっていったらいいかについては、生きることも死ぬことも選択できればいいと思います。
長く生きていることがいいという前提で物事は発展してきたけど、本当にそれが幸せなんだろうか、ということは結構多くの人が感じると思う。だから、逆に死の希少価値が上がったんです。なかなか人が死ななくなったことで、死はレアなものになった。
コロナ禍と死生観
——— これから死がどうなるかということはたしかに予測できないかもしれません。ですが直近で目に見える変化として、コロナ禍の到来があります。前田さんの視点からは、コロナ禍で人の死というものはどう変わったでしょうか。あるいは、変わっていないとお考えでしょうか?
「コロナで生が身近になった」と言われますが、「身近になったのは数字上でだけじゃん」と思いますね。死亡者数も数字だけで表されている。確かにコロナ禍で身近な人を亡くした方もいるかもしれませんが、多くの人はそうではない。
遠くに住む親戚などの人が亡くなったら訃報の連絡などに接すると思いますが、基本的に 亡くなったという情報そのものにはリアリティがない です。そもそも、会ってないのと死んでいることにあまり変わりがない。死を捉えるのには、想像力だけだと厳しいですよね。死を意識する機会は増えたものの、その死自体は曖昧になったと思います。
コロナ禍の前には、お葬式に行ったりしましたね。この前まで生きていた人のために、なぜか喪服を着て、なぜか香典を包んで、式場に行く。式場ではご遺体に対面して…など、死を理解するためのプロセスが多くあった。でもコロナ禍に入り、そうした理解のプロセスは省かれつつあります。「ごく身近な親族だけでやります」と言って、遠い親戚や故人の友人は連絡だけ受け取るわけですが、「亡くなった」という実感は湧きづらくなっている。
——— 確かに、この前僕の知り合いの方が亡くなりましたが、高校を卒業して以来一度もあったことがなかった方で、連絡を受けてもただ戸惑うだけでした。悲しいといった感情よりもまず、実感が湧きませんでした。ショックでしたが、それが悲しみなどに結びつかなかったです。
そうですね。
——— お話にあったように、コロナ禍でこれからお葬式はよりコンパクトになっていくと思われますが、そのことについてはどう思われますか。
これは時代の要請に応えた合理的なことだと思います。そもそも、ご近所付き合いが都会だとほとんどない中で、そしてコロナもあって一つの場所に同じ時間で集まることが難しくなっている。昔は活動範囲が狭かった分ご近所づきあいというものは多かったと思いますが、今では世界にもいけるし、どんどん活動範囲は広くなっている。だから、一つの場所に同じ時間で行う葬式が難しい中で、お葬式が小さくなっていくのは合理的なことだと思います。
そこで考えたいのは、どうやって 血縁以外の人の死を、つまりお葬式という場所で得ていた死のリアリティ、手触り感を補完するか ですよね。別に補完しなくてもいいという考え方もあるかもしれませんが。しかし死のリアリティを感じる機会がなくなっていくと、死が曖昧なものになっていってしまうと思いますね。
死に触れることで人は「締め切り」を意識できる
——— あえてお聞きしますが、死が曖昧であることはいけないことなのでしょうか?ある種の快適な暮らしの実現であると思いますが。もし人々が死というものを考えなくなったら、どういう問題があるのでしょうか。
死が見えなくなった社会を否定するつもりはありませんが、人は必ず死ぬわけじゃないですか。人の死を見る、つまり人は死んで硬くなって棺に収められるところを見て、自分が死ぬと具体的に自分がどうなるのかを知りますよね。
確かに死ぬことを意識しなくても人は生きていけますが、死というものを考えないと、締め切りを意識することがなくなってしまう。締切があるから仕事をすることができるように、死という締め切りを意識しなければ、良く生きることができないんじゃないかと思います。
ある意味、葬式などの機会で死を意識することは、死を活用して、 他者の死を足場にして人間は生きていきてきた んだと思います。命のサイクルとしてはそういうふうに人は生きてきたんだと思います。
もちろん本人は足場にして利用しているつもりはないかもしれませんが、死というものは少なくともそういうものとしても機能してきました。
——— 「死を活用する、足場にする」というのは人によっては抵抗感のある表現かもしれませんが、確かに他者の死を目の当たりにすることで人は自分の締め切りを意識し、「死ぬまでにこれはしよう」のような、よく生きるためのことを考えるきっかけを得ていたのかもしれません。
死と出会いたくない人にとっては、そのままでいる方が幸せかもしれません。それは人によって違うと思います。少なくともむじょうにおいては、死は活用できるものだし、死が近くにあった方がより良く生きることに役立つという前提に立って動いていきたいと思います。