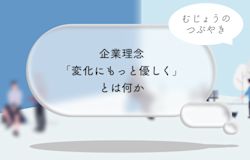連載:トイナオ死 #0「死を問い直す」

かつて、死は日常的なものであった。葬式は村総出で行われ、 個人の死は家族を超えて共有 された。そうした過程で人は死を意識し、時には恐れることで自らの人生について考えていたとされる。
しかし、現代の日本において、死、とりわけ 葬式は分業化とアウトソーシングが進み、日常の光景から失われつつある 。病人や高齢者は病院や介護施設に隔離され、その道の専門家・プロフェッショナルに委託される。御多分に洩れず、死は近代化したのである。
こうした変化は、遺族の負担を減らし、公衆衛生を向上させるなどして多くの恩恵をもたらした一方で、人々は死を自らのものとして引き受けることから遠ざかってしまった。
さらに、凄まじい速度で進化するテクノロジーに人々は追いつけないことで、生命倫理など様々な場面で「問う」という行為は置き去りにされている。また、 「わかりやすさ」礼讃の時代 が到来し、死や生といった根源的な問いの難しさと向き合う機会はますます減少しつつある。
大きな消費的な時代の流れの中に我々は飲み込まれ、問うべき重要なことと向き合えていないのではないか——— そうした危機感から、人々が死をはじめとした根源的な問い(自らの人生の理想的なあり方や幸福観、死生観など)に向き合う機会を作ること、つまり人々が「生きること、死ぬということを問い直す」ための一助となることを目的として、本連載はスタートした。連載のタイトルである『トイナオ死』は、「死を問い直す」ことをテーマとしていることに由来する。
ここまで語ってきたように、死を問い直すことで死を日常に取り戻し、ゆるやかに生活へと溶け出させることが本連載の究極の目標である。
もう少し死についての話を続けさせてほしい。
村上春樹は代表作『ノルウェイの森(上)』(講談社、1987年)で次のように書いている。
死は生の対極としてではなくその一部として存在している。
自分には縁のないものとして死を遠ざけるのではなく、生の延長線上にあるものとして死を捉えること、向き合うこと。社会現象にもなったこの小説は、現代人に対して死と向き合うことの意味について力強いメッセージを突きつけたように思える。
しかし一方で、死と向き合うことは、もちろん、痛みを伴うものである。いたずらに死と向き合うことを強要することは、誰の幸せにも繋がらない無意味なことだ。人々の気持ちに寄り添いながら、共に考えるという姿勢を忘れてはならない。
だからこそ、本連載では「共に考える」ために、人との対話を重視している。
テキストを介したコミュニケーションは、どれだけ内密なものであったとしても、どこか乾いていて、〈私〉の言葉でないような感じがしないと思ったことはないだろうか。
「死」という人間にとって最も根源的な概念について語る時、我々はつっかえたり、あるいは言葉が出なかったりする。そうした「声にならない声」は、テキストにはあらわれないが、死、そしてその先にいる人と向き合う上で、なくてはならないものだ。
哲学者の鷲田清一はこうした〈場所〉について、以下のようなことを書いている。
(哲学の場所とは)主体が他者とおなじ現在においてその他者とともに居合わせていて、その関係から一時的にもせよ離脱することなく、そこで思考し続けることを要求されるような、そういう場所のことではないだろうか。
——— 『聴くことの力』(ちくま学芸文庫、2015年)一部筆者により改変
哲学に限らず、死について語る場所は「むき出しの他者」と居合わせるものであるべきだろう。テキストでのコミュニケーションにはない共時的、共場的な空間は、対話によって初めて実現する。
そこで、『トイナオ死』では、死について関わる様々な人を訪ね、インタビューを行っていく。読者の方には、その記録を辿ることを通して問いと向き合ってみてほしい。また、これからの連載を通して、記事に対する批判や疑念などあればぜひ遠慮なく寄せてほしい。それもまた一つの対話なのだから。