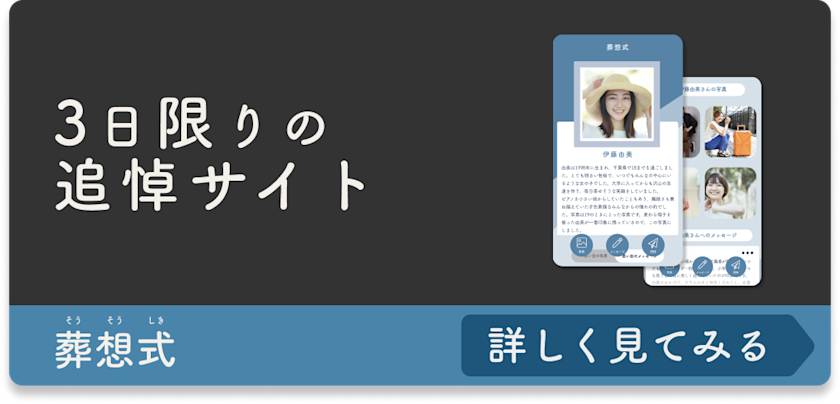忌明けとは?故人を偲ぶ大切な期間の意味としきたり

「忌明けまで祝い事はよくない」などと耳にして、「忌明けとは何だろう」と疑問に思う方も多くいらっしゃることでしょう。
忌明けとは、忌中の最終日を指します。忌中とは故人が亡くなってから49日間のことです。四十九日法要という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、四十九日法要が終わると忌明けになります。
今回は忌明けの意味やしきたりについてご紹介するので、ぜひ最後までお読みください。
忌明けの基本的な意味とは?
忌明け (きあけ、いみあけ)とは、遺族が故人の冥福を祈って喪に服す「忌服」の期間を終えることを指します。
昔、忌中は家にこもって故人のために祈り、けがれを祓う期間とされていました。最近ではそこまで厳しくはありませんが、結婚式やお祭りなど祝い事に参加することは禁止。神社などの鳥居もくぐってはいけないとされています。
忌明けの日程と期間
忌明けの日程は地方により変わるところがあります。しかし一般的には、亡くなった日を 「1日目」 として数え、そこから49日目が忌明けになります。
地域によっては、49日前日に行われる「お逮夜(おたいや)」がそのまま法要として根付いた経緯から、亡くなった日の前日を「1日目」と数えるところもあります。
忌明けに行う四十九日法要の流れ
四十九日法要の流れは以下のようになっています。
-
四十九日法要
法要の開始時刻は 午前10時ごろ からが多いようです。みんなが集まりやすく、かつ法要の後、会食を設けやすい時間帯のためです。 -
開眼供養
開眼供養とは、 お墓や仏壇、位牌を新たに購入した場合に行なわれる法要のこと です。
四十九日では、葬儀で使用された白木位牌を本位牌に魂を移し替えるので、開眼法要が必要になります。お墓の開眼供養は、納骨の前に行われます。 -
納骨法要
納骨法要とは、 骨壷をお墓や納骨堂に納めるときの儀式 です。 -
お斎
法要が全て終了すると会食が行われます。これは お斎 (おとき)と呼ばれ、法要の列席者や僧侶に食事を振る舞い、みんなで故人を偲ぶ時間を取ります。
忌明け前にしたほうが良いこと
忌明け前にしておいた方がいいことは、 「神棚封じ」 です。
「神棚封じ」とは自宅の神棚に白い半紙を貼り付け、忌明けまでお供えや参拝は控えることを言います。神棚には神様が宿っているとされていますので、けがれた「死」から神様を遠ざけるために、神棚封じは行われます。
神棚封じは家に死者が出たその日から、忌明けまで行います。
仏壇も閉めておくケースが多いですが、「死」をけがれたものとするのは神道の価値観だから仏教に関する物には影響がないという考え方もあり、仏壇はそのままにするという家庭もあります。また、宗派によっても考え方が違います。
毎日の供養
初七日までは、遺骨と位牌を安置しておくための仮の祭壇 「後飾り」 が必要となります。
後飾りは、初七日が終わったあとも四十九日法要まではそのまま飾っておきます。
忌明けまでは後飾りに向かい、毎日手を合わせてお水とお線香を焚くことが毎日の供養です。
水は毎日変えて、お線香は四十九日までは24時間絶えずつけておくのがよいとされてきました。しかし最近では、お線香についてはそうこだわらなくてもよいと考える人がほとんどです。核家族が中心となった現代においては忌中の間も家を空けることが多いため、線香を絶やさないのは難しいからです。
7日ごとの法要
- 初七日(しょなのか)
亡くなってから7日間、故人は香を食べてとても険しい山を歩いて行くとされています。なので、現世では お香を焚く ことになっています。
初七日では秦広王(しんこうおう)によって、生前にどんな殺生をしてきたかについて調べられます。
この裁きの結果により、三途の川の渡り方が激流の中を歩むのか、緩流の中を歩むのか、橋の上を渡れるのかが決まります。その際の渡し賃に六文かかるため、棺の中に六文銭を入れるのだとされています。
また、故人の両肩には倶生神(ぐしょうじん)という神様が宿っていて、一神は善行、もう一神は悪行を監視しています。
秦広王は両肩の倶生神の報告を聞き、帳面に故人の生前の行いを書き入れます。これが俗にいう「閻魔帳」です。それを次の王に引き継ぎます。
-
二七日(ふたなのか)
三途の川を渡り切った川岸には奪衣婆(だつえば)という老婆の鬼がいます。そこで衣服を剥ぎ取られ、その衣服は懸衣翁(けんえおう)という老人に手渡されます。
衣服は生前犯した罪の重さを計れる衣領樹(えりょうじゅ)という木にかけられます 。 -
三七日(みなのか)
文殊菩薩は、「三人寄れば文殊の知恵」で知られていますが、極楽浄土へ行ける知恵を授けてくださいます。
3度目の裁きは、 化け猫とヘビを使って不貞行為の罪を問うもの です。
もしも罪を犯していた場合は、化け猫や蛇に襲われ、その罪を悔い改めなければ衆合地獄に堕ちてしまうと言われています。
- 四七日(よなのか)
伍官王が審判となり、ここでは 生前どれだけ悪い言動をしたか、その重さをはかる秤 (はかり)があり、故人はそこに乗せられ、測られます。
また、伍官王の「伍官」とは目・耳・鼻・舌・身のことを指しており、人はこれら伍官を使って他人を欺き、傷つけることができるとし、その罪の重さを見極めます。
-
五七日(いつなのか)
かの有名な閻魔王が、水晶からできた鏡を使って故人の生前の悪行を映し出し、嘘をつく人の舌を鬼に抜かせてしまいます。
そして閻魔王は、 故人が生まれ変わる先を決定します 。 -
六七日(むなのか)
伍官王と閻魔王の報告から、変成王によって 生まれ変わるための条件、場所など詳しく決められていきます 。 -
七七日(しちなのか)=四十九日
亡くなってから四十九日目にあたるこの日は、とても 大切な法要の日 です。
これまでのすべての裁判の結果をもとに、泰山王が最終決定を言い渡す日でもあります。
その決定によって故人は中陰の世界を去り、天道、人間道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道のいずれかに生まれ変わるため旅立つと言われています。
四十九日法要には、家族や親戚が集まり、故人の供養を祈ります。それは、来世に少しでも良い世界に生まれ変わってもらうためでもあります。
役所関連の事務手続き
四十九日以内にやらなければならない事務手続きをご紹介します。
-
世帯主変更届
世帯主変更届は、住民基本台帳法という法律で 14日以内に提出が必要 だと定められていますので、早めに出しましょう。 -
年金受給の停止
年金を貰っている方が亡くなった場合は、 年金を受ける権利がなくなります 。
ですので、受給権者死亡届を地域の年金事務所に提出します。
故人がまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金は、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
-
国民健康保険証資格喪失届
健康保険に加入している方が死亡した場合は、 資格喪失手続きが必要 になります。
故人が国民健康保険に加入していた場合は、死亡から14日以内に 国民健康保険資格喪失届を市区町村役場に提出しましょう。 -
クレジットカードの停止
契約者が亡くなった後も解約をしない場合、年会費は請求され続けます。年会費がないカードはいいですが、 年会費を払っている場合は早めにカードを停止しておくのが良いでしょう 。

また、そのままにしておくと不正利用されてしまうリスクもあります。
そのため、契約者が亡くなられた場合には速やかにカード会社に連絡を取り解約手続きを行いましょう。
- 公共料金の解約
ガスや水道、電気を解約する場合は、所管の事業所や営業所に対して、解約をしたい旨の連絡が必要です。
身内が亡くなって葬儀がひと段落すると、遺品の整理や故人の部屋の片付けなどで電気、水道などを使用することも考えられますので、 日にちに少し余裕を持たせて解約日を設定しておくとよい でしょう。
忌明け前に慎んだほうが良いこと
ここからは忌明け前に謹んだ方が良いことをご紹介します。
基本的に忌明けは 「祝い事」がタブー です。
新年のお祝い
新しい年を迎えることは、謹賀新年と書く通り、おめでたいことです。
忌明け前の場合は、年が明ける際も謹んで過ごしましょう 。
また、11月から12月初めあたりまでに年賀欠礼状を出しておくと、送り先にも事情が伝わるので安心です。
新年の挨拶も本来ならば控えたほうがよいものですが、「おめでとう」というお祝いの言葉を使わなければ、普段通りの挨拶でも問題ありません。
例えば「新年を迎えまして今年もどうぞよろしくお願いします」「昨年は大変お世話になりました。今年もどうぞよろしくお願いします」などが無難な挨拶です。もし気になるようであれば、「こんにちは」程度に留めておくとよいでしょう。
また、門松やしめ縄などの正月飾りは出さない、おせちは重箱ではなくて大皿で出すなど祝い事のようにならないように工夫をしましょう。
親戚のお子さんにお年玉をあげるときも、「お年玉」ではなく、「おこづかい」と書いた袋に入れたり、現金を手渡しにしたりする配慮が必要となります。
神社への参拝
忌明け前は、神との関わりは避けたほうがよいとされています。
なので、神社への参拝は一般的にNGです。
お寺に行き、ご先祖様のお墓を訪れる程度なら問題はありません 。
結婚式やお宮参り
結婚式といえばお祝い事の代表例です。
ですので、 忌明け前は避けたほうが無難 とされています。
「どうしてもこの日に挙式をしたい」など、日付にこだわりがある場合は、挙式ではなく、入籍に留めておくのが無難です。
また結婚式に招かれた際も、忌明け前は断るのが一般的です。結婚式の招待状には、「諸事情により今回は欠席させていただきます。」など言葉を濁して書いておきましょう。
日を改めてお祝いの品などを贈れば、気持ちも伝わるでしょう。
お宮参りの場合、お祝い事は避けたほうがいいので、どうしてもの場合はお参りはせず、写真撮影だけに留めておくなどしましょう。
慶事や宴会などへの出席
忌明け前は、派手なこと、華美なことは避け、身を慎んで生活するのが良いとされています。
ですので、 慶事や宴会などのお酒の席、華やかな集まりに参加するのは控えましょう 。
誘われた際には身内を亡くして間もないことを伝えれば、理解してもらえるでしょう。
新築改装工事や引っ越し
住宅建築で基礎工事が始まる前には地鎮祭という祭事があります。その土地に家を建てて住むことを神様に報告し、安心安全に暮らせるよう願う儀式をおこないます。
忌明け前はなるべく地鎮祭を行うことは控えましょう 。
すでに契約していて工期が伸ばせない場合は、依頼している施工会社に相談しましょう。
場合によっては、お祓いを受ければ地鎮祭は可能、仏式の地鎮祭なら可能、など、忌明け前でも対応していただける場合があります。
なお、新築だけではなく、増改築も同様ですので、注意しましょう。
お中元やお歳暮
相手が忌明け前の場合はお中元やお歳暮を送ることは避けたほうが良いでしょう 。
忌明け前は、まだ相手先がバタバタしていたり、故人との別れに心の整理がついていなかったりする可能性があるので、あまりいいタイミングではありません。
もらった側はお返しを用意しなければならず、忙しい時期には大変です。
また、自身が忌明け前の場合も無理して送る必要はありません。

まとめ
今回は疑問の多い忌明けの意味やしきたりについてご紹介しました。
忌明け前は色々と縛りがあり、やることもたくさんあるので忙しい時期ですが、ご自身の体も気遣って過ごしましょう。