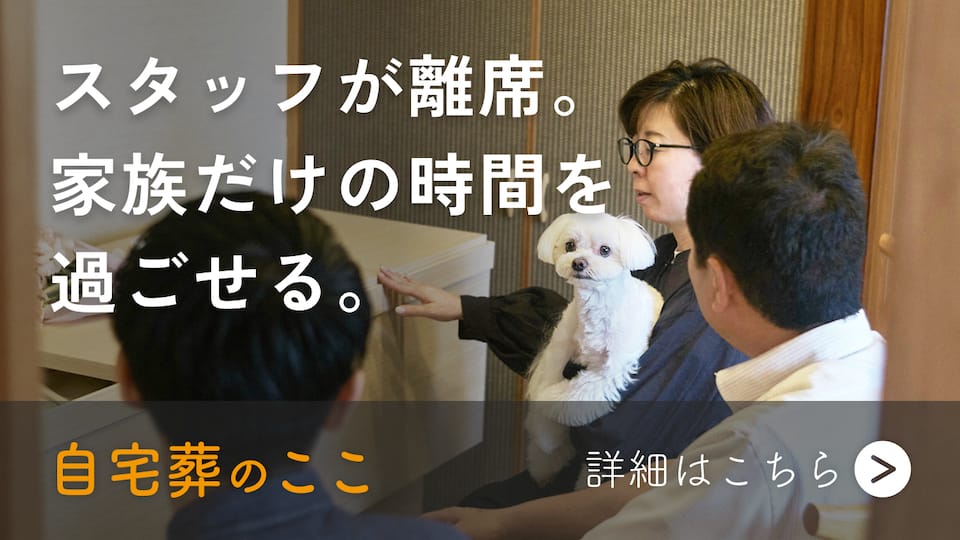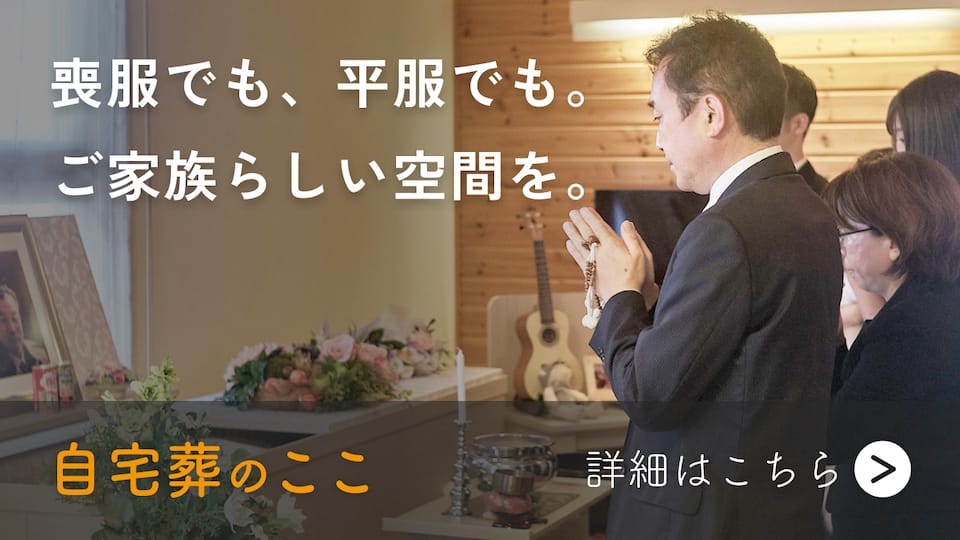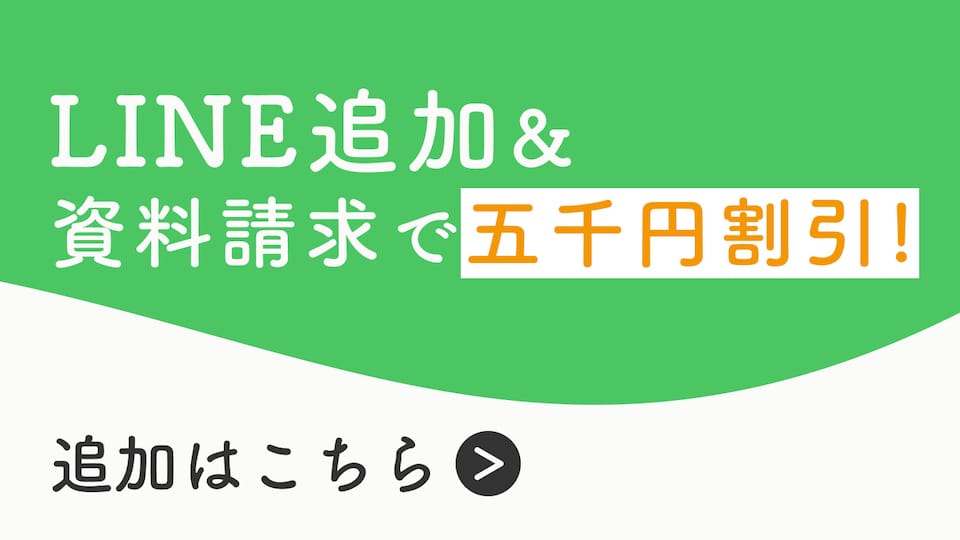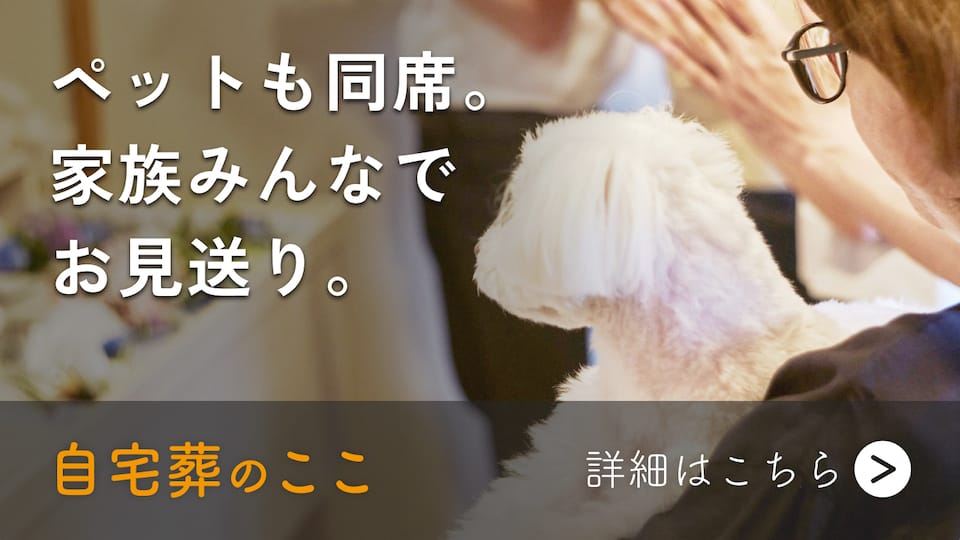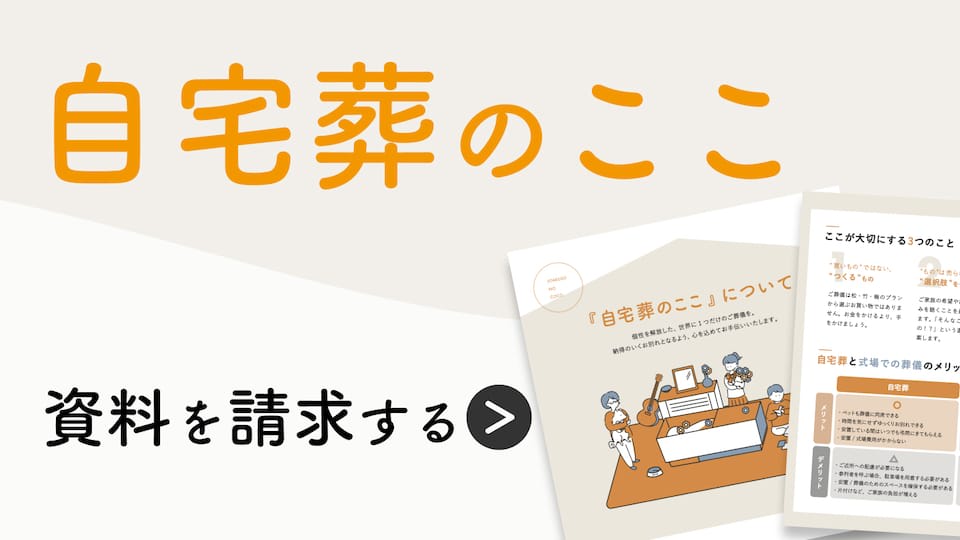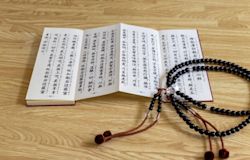一日葬の流れは?内容・費用・注意点についても解説

一般的な葬儀は「お通夜」「葬儀」と2日間ほどかかりますが、最近は新しい形の葬儀、「一日葬」というものがあります。今回は、そんな新しい形の葬儀についてご紹介させていただきます。
一日葬とは
一日葬とは、一言で言うとお通夜がない葬儀のことです。お通夜を省き、告別式と火葬を1日で執り行います。
一般的な葬儀は、1日目にお通夜を、2日目に告別式と火葬を行うことがほとんどですが、一日葬の場合は1日で葬儀を終えられます。
そのため、喪主や遺族の負担も軽くなり、少ない人数でひっそりと葬儀を終えたい場合などに適しています。また、遠方からの参列者は、開式時間によっては宿泊することなく日帰りで参加することも可能になります。
一日葬の流れ
逝去・安置
病院や施設などで亡くなった場合は安置場所へ移送されます。安置はご自宅か葬儀社施設、もしくは公営、民間の安置施設になります。施設の空き状況やご自宅の環境にもよりますが、ご家族の希望で決めることが可能です。
法律により、亡くなった後の 24時間は火葬ができない ため、亡くなったその日のうちに葬儀がおこなえるわけではありません。
葬儀社との打ち合わせ
安置が終わり次第、葬儀の担当者との打ち合わせに入ります。打ち合わせでは、一日葬での葬儀を希望している旨を担当者に伝えましょう。
それに合わせて火葬の空き状況や僧侶のスケジュール確認を行い、一通りの流れを決めていくこととなります。
打ち合わせでは主に以下のことを決めていきます。
- 葬儀形式
- 日程
- 予算
- 葬儀会場

納棺
納棺とは、お見送りをするにあたって、故人様の身なりを整えてお棺に納めることです。納棺士がお着替えやお化粧直しをいたします。希望によりご遺族に手伝ってもらうことがあります。
葬儀・告別式
納棺後、あるいは納棺の翌日、葬儀、告別式が開式されます。一日葬の場合お通夜は行わないので、行われるのは葬儀・告別式のみとなっています。
葬儀は家族の希望に沿った式を執り行い、最後に花入れを行い出棺し、火葬場へ向かいます。

火葬
僧侶がいる場合、火葬前に読経を行い、喪主から順に焼香をします。火葬後は骨上げ、散会となります。
精進落としを省略する場合、火葬後はそのまま解散になります。場合によっては、火葬場から葬儀式場に戻り、初七日法要を行うことがあります。
1日葬の場合の菩提寺への連絡
葬儀は宗教行事です。葬儀は基本的に、お通夜、告別式、火葬という流れを重視しています。なので、お通夜のない一日葬は新しい形のため、菩提寺で受け入れられない可能性があります。
遺族の意向が何よりも大切ですが、葬儀日程を決めてからトラブルにならないように、あらかじめ菩提寺に確認しておくと安心でしょう。
1日葬のメリット・デメリット
メリット
一日葬では、お通夜は行いません。そのため、葬儀が1日で終えられるため、遠くに住む遺族に宿泊先を手配する必要もありません。また、食事や会葬礼品などの用意も、遺族や少ない参列者の分だけを用意することになります。
デメリット
1日のみの葬儀となるため、参列者が限られるでしょう。一般的な告別式の開始時間は、11時または正午あたりです。よって、仕事のある方は葬儀に参列できなくなることも少なくないでしょう。もし、遺族のほかに大切な参列者がいる場合は、都合がつくかどうかを事前に確かめておく必要があります。
前述のように、一日葬を検討する場合は、遺族の意向だけで決めるのではなく、菩提寺などに事前に相談を入れておくことが必要でしょう。
また、斎場を利用する場合、1日のみの使用でも2日間の使用料がかかる場合があるので、そこも注意しておきましょう。
まとめ
今回は、新しい形の葬儀「一日葬」についてご紹介しました。新しい形の葬儀なので、デメリットとしてあげられることも多いですが、少人数で静かに葬儀を行いたい場合や、遠方からの参列者が多く、休みが取りづらいといった場合などに適していると思います。
今回の記事を参考にぜひ一日葬を検討してみてはいかがでしょうか。